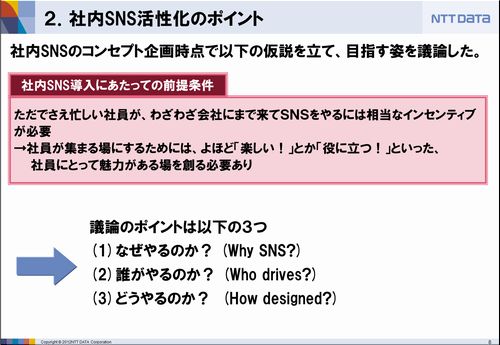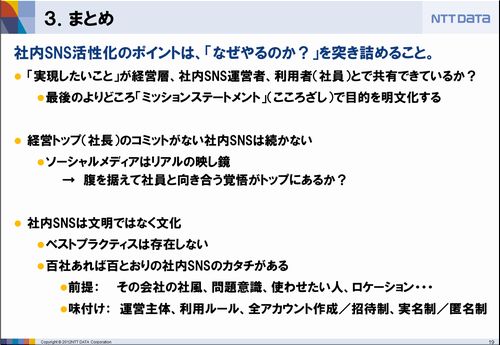3/15に行われた、
【若手・ベテラン社員「脱あきらめマインド」の秘策】
(主催:日経BPマーケティング、共催:ToBeings)
というセミナーに参加しました。
セミナーの詳細は、右の画像をクリックして、
紹介ページをご覧ください
私が参加した動機は、最近考えている、ナイスミドル(もっと、ベテラン社員が、トップと若者の”継ぎ手”になろうという活動)の参考になるかもしれないと思ったからです。
結論から言うと、参加前に思っていた内容とは少し違いました。
けど、ものすごく有意義でした。
今後のナイスミドルの会の活動や、私自身の生活に大きな影響を与えたと思います。
内容は、
管理職前のベテラン社員には、表面的には、先が見えてしまったことによるモチベーションダウンや、新しいチャレンジに対するあきらめ感が蔓延しているように見えます。また、次世代の管理職となるはずの若手社員の一部には、プライベートで見せている情熱とは裏腹に、仕事に対しては妙に冷めてしまっていて、与えられた仕事をこなす以上のやる気がなかなか見えて来ないように見えます。
という状況に対して、以下に接していくか?というものでした。
(私は、ベテラン社員があきらめマインドの若手にどうアプローチするか?という内容だと思ってた)
このセミナーで、私が得たものは、2つです。
1つ目は、 ”あきらめ層をあきらめるな”
2つ目は、”関係の質の改善のためには場の質が最重要”
1つ目の”あきらめ層”というのは、 上述のベテランや若手のことです。
(セミナーでも講師の橋本さんが、こういうレッテル張るような言い方は望ましくないのですが、
他に良い言葉が見つからなくて・・とおっしゃってました。
私も便宜上、この言葉のまま記載します)
セミナーの中でロールプレイをしたのですが、”あきらめ層役”の方々の演技が
素晴らしくて、何回も途方にくれました。
けど、あきらめずに対話を進めていると、すこし糸口が見えてきました。
そこからはズルズルと辿って行って、ついに穴から引きずり出し、
最後は、一緒に日本を支えようぜ!ってところまで持っていきました。
ロールプレイ後、それぞれのシナリオを付け合せて、検討したのですが、
全員、”ファシリテータ役の方が一生懸命、若手の言葉を拾ったのが良かった”と
いう意見でした。
やっぱり、”あきらめたらそこで試合終了”なんです。

2つ目の関係の質というのは、
Daniel Kimさんの「成功循環モデル」というものに出てくるそうです。
関係の質→思考の質→行動の質→結果の質
が、循環して影響するというモデルなのですが、
実は、関係の質を改善するためには、
そこが、安心・安全な場であることが必要だそうです。
今回のセミナーのグループ5人は非常に打ち解けていて、グループ討議もなかなか有意義な内容になりました。
最近、知っている人がいないイベントに出かけることは少なかったので、私もかなり緊張していたのですが、
なんで、こんなにもいい関係になるのだろうと思ったら、”場”が良かったんですね。
ソーシャルメディアに携わっていて、ワールドカフェなどにも参加したことがあるので、
少しは分かっているつもりでしたが、改めて実感しました。
頑張って書き留めたノートには、まだまだいろいろとキーワードがあるのですが、
うまく言語化できないので、中途半端にお伝えするのは控えます。
>グループのみなさん、
今回は非常に面子に恵まれました。本当にありがとうございました。
また、どこかでお会いすることを楽しみにしています。
社内SNSについての疑問や相談はいつでもご連絡ください。
>講師の橋本さん
話の幅が広く、プレゼンがうまくて、かなりわかりやすかったです。
ありがとうございました。